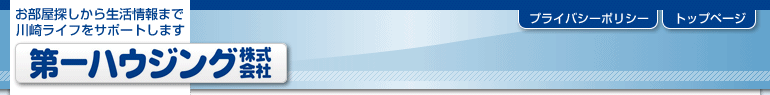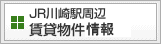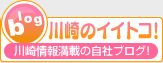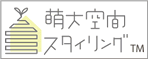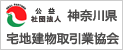建物の耐震性を知る
2016年6月17日掲載
 2016年度「全国地震動予測地図」が公表されました。今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率の分布を示したものです。
2016年度「全国地震動予測地図」が公表されました。今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率の分布を示したものです。 各地点の確率は防災科学技術研究所のサイト「地震ハザードステーション」で公開されています。 http://www.j-shis.bosai.go.jp/news-20160610
関東地方はほぼ横ばいで推移しているとはいえ、県庁所在地周辺の数値で横浜市の確率は81%。非常に高い確率に驚かされます。
<耐震基準の変遷>
賃貸経営をされているオーナー様にとって、所有する建物の耐震性については、よくある心配事の一つです。特に築年数の経過した建物を所有の場合、地震が起きるたびに漠然とした不安が起きてくるのではないでしょうか?
建物の耐震基準は、その建物がいつ建てられたかにより基準となる耐震性が大幅に違ってきます。
耐震基準について、「旧耐震基準」「新耐震基準」と言われますが、「旧耐震基準は」建築基準法が制定された1950年に定められた耐震基準です。その後大地震のあるごとに見直され、1981年6月に耐震性の基準が大きく変更されました。これがいわゆる「新耐震基準」です。「新耐震基準」ではきわめてまれに起こる地震によっても建物が倒壊しないことが前提となりました。
その後さらに大きく基準が変更されたのが2000年6月です。この改正は特に木造建築物における耐震性についてより厳しく変更されています。事前の地盤調査が義務化され、木造建築物における留め金具などの金物の種類や、耐力壁について具体的に示されています。
物件の建築時期が旧耐震基準で建てられたと判明した場合は、専門家による耐震診断、耐震補強を行うことをお勧めします。また、特に木造アパート等の場合は、1981年以降2000年までに着工したものは新耐震基準だからと安心せず、現行の基準で建てられているものよりも耐震性が低いと思われるため、不安を感じる場合は専門家の診断を仰ぐことをお勧めします。
 <耐震診断とは>
<耐震診断とは>
現地建物を目視で調査、設計図面等の内容を確認、さらに使用履歴や劣化診断などデータによる計算で行われます。現地調査は非破壊で行い、入居者が居住中でも実施可能です。場合によっては入居者の協力が必要になることもあります。
耐震診断の結果、耐震性が低いことが分かった場合、補強工事や耐震改修工事が必要になります。マンションなどの場合は工事を含めた大規模修繕のタイミングを検討していきます。
<自治体による助成>
川崎市では木造住宅の耐震診断・耐震改修について一定の条件を満たす場合、市が費用の一部を助成しています。また、マンションについても同様に一定の条件を満たす場合に費用の一部を助成する制度があります。
詳しくはこちら http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/24-4-17-0-0-0-0-0-0-0.html
参考:全国賃貸住宅新聞 ㈱全国賃貸住宅新聞社 川崎市HP
このページのトップへ▲
これからの賃貸経営 ~超高齢化社会で想定されること~
2016年5月16日掲載
 これから超高齢化社会となっていく日本で、高齢者の独り暮らしは珍しいことではありません。また、高齢化が進んだ中で賃貸経営をしていくと、入居者が賃貸物件で老衰または病気で亡くなってしまうケースもあるかもしれません。
これから超高齢化社会となっていく日本で、高齢者の独り暮らしは珍しいことではありません。また、高齢化が進んだ中で賃貸経営をしていくと、入居者が賃貸物件で老衰または病気で亡くなってしまうケースもあるかもしれません。
●告知義務
入居者が亡くなってしまうケースには自然死のほか事故死、自殺、他殺があります。そのような物件では、次の入居者へ告知をしなければならない場合があります。通常、自然死以外の場合、一般的にはその部屋に住むことが何となく嫌な気持ちがする…という心理的瑕疵物件に該当するため、告知義務があります。
では、近年心配される孤独死は告知義務がないのでしょうか? 一般的に孤独死は老衰や病気で亡くなる自然死と考えられ、告知義務はないとされています。しかし、孤独死で死後ご遺体が放置され、腐臭や汚れが生じてしまった場合など、遺体の状況によっては心理的瑕疵に該当するような状況もあると考えられます。告知義務の有無についてはケースバイケースで明確な基準が設けられているわけではありません。今後ますます高齢化が進む中で、留意しなければならないと考えられます。
●損害賠償
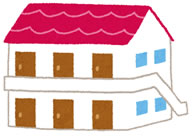 賃貸物件の入居者は、賃貸借契約における基本的な義務として、適切な注意を持って賃貸物件を利用する義務(善管注意義務)を負っています。
賃貸物件の入居者は、賃貸借契約における基本的な義務として、適切な注意を持って賃貸物件を利用する義務(善管注意義務)を負っています。
例えば、入居者が自殺により賃貸物件で亡くなってしまった場合、自殺は入居者が自らの意思で賃借物件にキズをつけてしまうものと考えられ、善管注意義務に違反したとして、賃貸人は入居者の相続人や保証人に対して一定の損害賠償を求めることができることがあります。
一方で、賃貸物件内で自然死により入居者が亡くなってしまった場合、過去の判例では、賃借人に善管注意義務の違反を認めることは出来ないと判断しています。自然死においては、自らの意思によってその部屋で亡くなることを選択したわけでも、自らの死を具体的に予測できたとも基本的に言えないからです。
とはいえ、賃貸物件内での自然死でも、期間の経過とともに悪臭や汚れが物件についてしまった場合、改修工事をしなければ次の住人に貸すことができません。こうしたケースにおいて、過去の判例では、賃借人は賃貸借契約が終了する際、部屋を借りた時の状態に戻して賃貸人に返す義務があるとして、物件の修理費用や工事期間の賃料相当額を賃貸人に生じた損害として認め、賃借人の保証人に対してその支払いを命じています。
賃貸物件内での入居者の死亡は、その原因や具体的な状況によってその後にとることのできる対応は様々です。今後社会全体の高齢化が進むと孤独死も増えると思われます。賃貸経営上避けては通れないリスクとして想定しておくことも必要になってきています。
参考「全国賃貸住宅新聞」 ㈱全国賃貸住宅新聞社 一部抜粋このページのトップへ▲
賃貸経営の法人化
~資産管理会社を設立した時のメリットと注意点~
2016年4月14日掲載
◆法人化には以下の3つがありますが、最近では個人の資産を減らす効果があるので相続対策を見越した③のケースが増えてきています。
| ①不動産管理型 | 個人所有の不動産を法人が管理します。個人所有は変えずに法人は管理報酬を得ます。 |
| ②一括借上型 | 個人所有の物件を法人が一括借り上げし、入居者に転貸します。法人は空き室でも借り上げます。 |
| ③不動産所有型 | 個人所有の建物を会社に売り、会社が貸主になります。売買の手続きが必要になるので、個人には譲渡所得税が発生し、法人には不動産取得税や名義変更による登記費用が発生します。 |
◆法人化のメリット
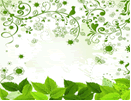 法人化による効果は所得分散をすることにあります。オーナー(被相続人)と親族(相続人)を役員にして報酬を支払うことにすると所得が分散されます。個人の所得税では累進課税のため、収入が多いと課税税率が高くなります。現在では課税される所得金額が1800万円~4000万円では税率40%、4000万円以上では税率45%となっています。法人税との税率の差を考慮すると法人を設立した方が節税となる場合があるのです。また、給与所得控除という非課税枠もあるので、より節税になります。
法人化による効果は所得分散をすることにあります。オーナー(被相続人)と親族(相続人)を役員にして報酬を支払うことにすると所得が分散されます。個人の所得税では累進課税のため、収入が多いと課税税率が高くなります。現在では課税される所得金額が1800万円~4000万円では税率40%、4000万円以上では税率45%となっています。法人税との税率の差を考慮すると法人を設立した方が節税となる場合があるのです。また、給与所得控除という非課税枠もあるので、より節税になります。
相続時を考慮すると、オーナー(被相続人)の財産を増やさず、かつ親族(相続人)の財産を増やすことができ、相続人は納税資金を蓄えることが可能となります。
また、被相続人が認知症になってしまった場合、個人所有の場合は資産を動かすことが難しいですが、法人所有の財産であればその心配はありません。
◆注意すべき点
 法人設立の際に登記費用など諸費用がかかります。
法人設立の際に登記費用など諸費用がかかります。
また、法人を設立すると社会保険の加入義務も出てきます。社員に給与の支払いをすると法人と社員が社会保険料を分割して負担します。社会保険料は支払う給与額によって変動しますが、支払う給与のうち約29%が法人と社員が支払う社会保険料です。例えば資産管理会社を設立して配偶者と子を役員とし、各30万円の役員報酬の支払いをすると、月額約26.1万円、年間約313.2万円の社会保険料の負担が必要になります。法人設立して所得分散し税率を下げたとしてもその効果が薄れてしまうのです。
最近では、マイナンバー制度の導入など、政府がこの社会保険未加入企業への指導強化をしている傾向がみられます。
尚、給与の支払いをしなければ社会保険料の支払い義務はないため、給与の支払いをせずに法人税を支払い、法人の所得として利益を蓄積することもできます。今後法人税は低下傾向にあるので、そうすると手残りが多くなります。
賃貸経営の法人化による納税・相続対策はケースバイケースで専門的な知識が必要です。検討される場合は必ず専門家へのご相談をお勧めします。
参考:「全国賃貸住宅新聞」 ㈱全国賃貸住宅新聞社このページのトップへ▲
物件の収納力UPのウラワザ
2016年3月24日掲載
 賃貸市場の繁忙期も終盤です。より選ばれる物件になるために何が出来るか・・・
賃貸市場の繁忙期も終盤です。より選ばれる物件になるために何が出来るか・・・常にニーズの高い「収納」について取り上げます。
●「収納」ニーズは高く、満足すると定着
モノは巷にあふれ、お部屋にもあふれ、断舎利でもしないとなかなかスッキリ出来ないのは世の常ではないでしょうか? 書店には多くの「片づけ本」も出ています。
「収納」は永遠のテーマ…とまではいかないですが、賃貸物件でも「収納が少ない」「収納が使いづらい」それだけでお部屋探しの選択肢からはずされてしまうケースは少なくありません。
逆に、入居者が現在の収納に満足している場合、長く住んでもらえる可能性が高くなります。
●賃貸物件の収納力をUPするには…
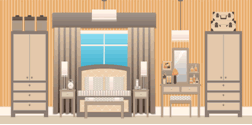 賃貸住宅では多くの場合、壁に穴を開けたり傷つけたりすることが禁じられています。棚に絵や雑貨を飾りたいと思っても外したあとの穴跡が気になってなかなかできないのが現状です。
賃貸住宅では多くの場合、壁に穴を開けたり傷つけたりすることが禁じられています。棚に絵や雑貨を飾りたいと思っても外したあとの穴跡が気になってなかなかできないのが現状です。
こうした入居者の悩みを解消する商品が出ています。
①ホチキスで棚を設置
一般的なホチキスを利用して石膏ボードの壁に取付けることができるもの。取付け金具一つにつき数カ所のホチキス針で固定し、金具に棚やウォールハンガーなどを掛けて設置します。ホチキス針を外しても虫ピンの穴より小さな跡しか残らないので、賃貸物件にはもってこいです。耐荷重6㎏~10㎏と商品バリエーションがあります。
②突っ張り棒のような柱を設置できる樹脂パッド
商品は樹脂製のパッドで、使用するには、設置する場所の天井高から約4.5cmカットした市販のツーバイフォー材の両端に取付け、垂直に立てて固定します。上部のパッドにはバネが付いていて設置しやすくなっています。2本使用して棚受けを取付ければ飾り棚となりますし、1本だけでもフックを取付けてカバンや帽子などの壁掛け収納として利用できます。工夫次第で様々な用途に使用でき、ツーバイフォー木材はペイントもできるので、ネット上にはオシャレに彩られたものが紹介されています。
入居者が物件をカスタマイズできるDIY物件などが最近は注目を集めていますが、そうした物件での利用価値は大きいと思います。
③デッドスペースを生かす
天井付近や梁下などのデッドスペースに取付けて使用するコンパクトタイプの収納ボックスが開発されています。A4サイズの雑誌などが収納できるように設計されており、居室やリビングに限らず、トイレや洗面所の上部スペースにも設置できるように圧迫感のない仕様となっています。
賃貸物件では、トイレや洗面所の収納が無いことが多く、入居してから不便さを感じることがありますが、そうしたところに設置することで使い勝手がUPします。内部には専用の棚を取付けることも可能で小物を整理しやすくなっています。
以上、様々に工夫をこらした収納商品が出てきており、低コストで取り組みやすいものもあります。
せまいから…収納スペースはムリ…とあきらめず、物件の収納力UPに役立ててみてはいかがでしょうか?
このページのトップへ▲
効果的な設備リフォームを考える…
2016年3月4日掲載
 賃貸市場の繁忙期を迎え、入居者のニーズが気になる季節となりました。いつの時代にも選ばれる物件であり続けるために、適時に設備・仕様を新しくしていくことは重要です。
賃貸市場の繁忙期を迎え、入居者のニーズが気になる季節となりました。いつの時代にも選ばれる物件であり続けるために、適時に設備・仕様を新しくしていくことは重要です。出来るだけ低コストで効果的な設備・仕様を導入するにはどうしたらいいでしょうか?参考となる調査結果を以下にご紹介します。
★入居者の設備利用経験と満足度から・・・
「入居者の設備利用経験の有無 と 物件に必要と考えている設備 と 満足度の高い設備」
| 必要度 | 経験率 | |
| エアコン付 | 71% | 96% |
| 都市ガス | 57% | 80% |
| TVモニタ付インターフォン | 44% | 62% |
| 追い焚き機能付風呂 | 41% | 58% |
| 温水洗浄便座 | 36% | 55% |
| 宅配ボックス | 27% | 35% |
| 無料or安価な高速ネット接続 | 24% | 25% |
| 保温機能付浴槽 | 24% | 34% |
| 防犯カメラ | 24% | 32% |
| 浴室乾燥機 | 23% | 42% |
②利用者経験者に聞く、設備・仕様の満足度
| 満足度 | 経験率 | |
| 食器自動洗浄機 | 100% | 7% |
| エコキュートなど省エネ給湯器 | 100% | 4% |
| LED照明 | 98% | 17% |
| 都市ガス | 97% | 80% |
| TVモニタ付インターフォン | 96% | 62% |
| 保温機能付浴槽 | 96% | 34% |
| ピッキング対策のカギ | 95% | 35% |
| 追い焚き機能付風呂 | 94% | 58% |
| 温水洗浄便座 | 94% | 55% |
| シャワー付化粧洗面台 | 93% | 40% |
③利用経験はないが必要度の高い設備
| 必要度 | |
| 都市ガス | 26% |
| 無料or安価な高速ネット接続 | 17% |
| 断熱・遮熱性能の高い窓 | 17% |
| 追い焚き機能付風呂 | 16% |
| TVモニタ付インターフォン | 15% |
| 無料or安価なWiFi | 15% |
| 遮音性能の高い窓 | 15% |
| エアコン付 | 14% |
| LED照明 | 13% |
| 温水洗浄便座 | 13% |
上の①~③表は入居者の設備利用経験と絡めて、設備の満足度、必要度でランキングしたものです。
①表では、物件選びの際に決め手となった設備トップ10です。経験率が50%以上の[温水洗浄便座]~[エアコン付]までの上位5位までは入居者にとって当然の設備といえます。リフォームする際は優先して導入すべき設備です
②表は設備の満足度のランキングです。光熱費を下げる設備や防犯関連の設備が挙げられています。
経験率は低いですが、満足度が高い上位3位までの[食器自動洗浄機][省エネ給湯器][LED照明]は他の物件にあまり導入されていないので差別化するためには効果的な設備です。
トップ10すべてが満足度90%以上なので、このうち経験率50%以上の設備[温水洗浄便座][追い焚き機能付風呂][都市ガス][TVモニタ付インターフォン]等は、入居者にとって魅力的なアピールとなる設備と言えます。
③表は設備利用したことがない人が必要と感じている設備のランキングです。②表同様、光熱費削減の設備が挙げられています。また、こちらでは[高速ネット接続][WiFi]などの通信設備、また断熱性、遮音性に関する設備が多く挙げられており、ネット環境と室内の快適性を求める傾向が出ています。
どの設備も入居者にとって必要または魅力的であることから、いかに効果的な設備導入をするかは物件の特性を見極める必要があります。
シングル向けかファミリー向けか、立地によっては男性・女性どちらの入居者が多いかなど、物件の特性を見極めて、ターゲットを絞り込むことで、より効果的な設備リフォームが出来ると思います。参考:「全国賃貸住宅新聞」 ㈱全国賃貸住宅新聞社 一部引用
このページのトップへ▲
ご存知ですか? 「財産債務調書」について
2016年1月19日掲載
 今年も間もなく確定申告のシーズン。オーナーの皆様は領収書の整理、チェックなど準備にお忙しいのではないでしょうか。
今年も間もなく確定申告のシーズン。オーナーの皆様は領収書の整理、チェックなど準備にお忙しいのではないでしょうか。さて、「財産債務調書の提出制度」についてご存知でしょうか? 平成27年度税制改正において創設されました。
所得税、相続税の申告の適正性を確保する観点から、財産及び債務の明細書を見直し、一定の基準を満たす方に対し、その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度です。平成27年12月31日現在の財産、債務については今年の3月15日までに提出となっています。
●提出義務者の要件 ~主に資産家・富裕層に提出義務があります~
| ① | 所得税の確定申告書を提出しなければならない方で、その年の所得金額の合計額が2000万円超である方。 |
| ② | その年の12月31日において保有する財産の価額が3億円以上であること。 |
| ③ | その年の12月31日において有価証券等の価額が1億円以上であること。 |
これまでも上記①の方は確定申告の際、「財産債務明細書」に自分の財産がどれだけあるかを記入して提出しなければなりませんでした。
今改正で、上記①に加えて②または③の要件を満たした場合に「財産債務調書」の提出義務があることとなり要件がさらに絞られました。これまで「財産債務明細書」を提出していても、今年は「財産債務調書」の提出義務がないという場合があります。
●記載事項について
 提出者の氏名・住所に加え、財産の種類、数量、価額、所在、債務の金額等となっています。財産の価額はその年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」とされています。財産の種類(土地・建物・預貯金・有価証券等々)により詳細な規定がありますので注意が必要です。
提出者の氏名・住所に加え、財産の種類、数量、価額、所在、債務の金額等となっています。財産の価額はその年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」とされています。財産の種類(土地・建物・預貯金・有価証券等々)により詳細な規定がありますので注意が必要です。
今年からはマイナンバー制度によりマイナンバーの記載もしなければなりません。財産や所得について、富裕層に対するチェックが厳しくなってきている表れとみられています。
●メリットや罰則等
「財産債務調書」を提出期限内に提出した場合で、記載された財産・債務について所得税・相続税の申告漏れが生じたら、過少申告加算税が5%軽減されます。
一方、「財産債務調書」を期限内に提出しなかった場合や、財産・債務の記載が不十分な場合に、その財産や債務に関して所得税の申告漏れがあった場合は、過少申告加算税が5%加重されます。
「財産債務調書」を提出しないことや虚偽記載について罰則はありませんが、上記のような措置が取られています。
従来の「財産債務明細書」の場合は、比較的ゆるやかな制度でしたが、税制改正により「財産債務調書」に変更されて、提出義務者は絞られましたが、より厳格になっています。資産家・富裕層の相続税、贈与税の申告漏れを防ぐための一手といえそうです。
詳しくはお近くの税務署・税理士にお尋ねください。
このページのトップへ▲
相続・承継の新たな手法 ~家族信託~
2015年12月10日掲載
 相続に関する「信託」について、一般的には信託銀行などで行うものをイメージする方が多いと思いますが、信託法の改正により、今は信託銀行を利用しなくても家族で信託が行えるようになりました。
相続に関する「信託」について、一般的には信託銀行などで行うものをイメージする方が多いと思いますが、信託法の改正により、今は信託銀行を利用しなくても家族で信託が行えるようになりました。信託銀行で行う信託を「商事信託」、家族で行う信託を「民事信託」と分けます。
●家族信託(民事信託)とは…
財産を持つ人が特定の目的(自分の老後の生活、介護、資産の管理・有効活用、資産承継など)に従って、その保有する不動産・預貯金等の財産を「信頼できる家族」に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
まずは財産を持つ親が元気なうちに信託契約を締結することが必要です。コストがかからないので、資産家のためのものだけではなく、誰にでも利用できます。
*基本的な登場人物
委託者:財産を預ける人
受託者:財産を預かり管理する人
受益者:財産の収益を受ける人
信託法において信託とは、委託者が信託行為(例えば信託契約、遺言)によってその信頼できる人受託者に対して財産を移転し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って受益者のためにその財産(信託財産)の管理・処分などをする制度で、節税対策ではなく、財産の管理手法です。現在の信託法は2007年に施行されています。
★事例:親が長男に信託財産の管理・処分を任せる ⇒ 認知症への備え
例えば、認知症になると預金の引き出し依頼や贈与、契約の締結など多くの法律行為が出来なくなり、財産の管理運用面で支障が出ます。
下図のように、親に代わり長男に財産の管理・処分を任せることで、認知症発症により判断力が低下しても財産の管理・処分が面倒な手続きなく可能となります。
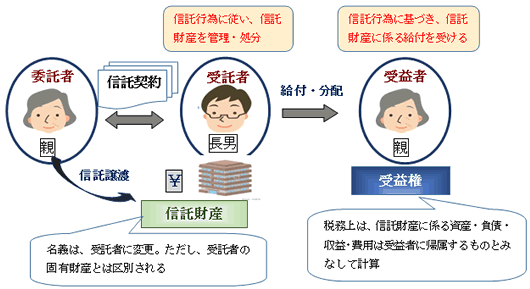 ★上記図の解説:
★上記図の解説:◎賃貸住宅を信託財産として長男に管理を任せた場合です。
財産を所有している親が委託者となり、信頼できる長男が受託者として両者間で信託契約を締結します。受託者である長男が契約に定めたアパートやマンションなどの信託財産の管理を担います。
信託財産から得られる家賃収入は、受益者である親本人のために管理し、必要に応じて受益者に給付します。
受託者の暴走を予防するために、司法書士等の信託監督人を置き、受託者に定期的な報告をさせることも可能です。
 ◎登記簿にはどのように記載されるか…?
◎登記簿にはどのように記載されるか…?
財産管理を担う受託者(上記図では長男)が形式的な不動産所有者として登記簿に記載されます。信託契約を締結すると所有権は信託受益権という財産に、所有者は受益者という立場に変わります。
税務上の所有者は受益者で、信託財産は委託者や受託者の財産とは分別管理されます。
さらに、資産の承継先を自由に指定できることや、民法では無効とされていた2次相続以降の財産の承継先を本人の意思で指定できるなど、信託による多様な可能性があります。
財産管理や資産承継の最も新しい手法の一つです。ケースバイケースで検討してみてはいかがでしょうか?